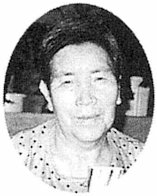 上富良野に生まれ育つ
上富良野に生まれ育つ大正五年七月、父北村留五郎、母かめじとの間に四人きょうだいの一人娘として佐川団体で出生、九歳まで育ち、日新尋常小学校に通った。勉強道具は風呂敷に包んで背負い、通学時の服装は、冬はモンペに綿入れ袢纏[はんてん]、赤ケット(赤い色の毛布)で膝までの袋を縫い、口を紐で結[ゆわ]え長靴の様にして履き、手にはテッカイシ(木綿地をミトンの型に裁ち中に綿を入れて刺した手袋)ネルの頭巾(御高祖頭巾[おこそずきん]のようなもの)をかぶった。
道路は曲がり曲がりの山道で、近道をしようと深雪の中を尻で滑り下り、一人が滑ると、みんなが歓声を上げながら後に続き、雪まみれになりながらも楽しい通学であった。
四年生になった時、西二線北三十一号に引っ越し間もなく十勝岳の爆発があった。
父は田圃で代掻き、母は家で味噌大豆を炊いており、私が学校から帰って、その豆をおやつに食べていると「ドーン!!」と大きな音がした。驚いて外を見ると、フラノ川の堤防の木が、どんどん倒れ消えて行った。向い側に土堤があったので家は難を免れ、母は「道遊びせずに帰って来て良かったー」と言ったが、あと何分か遅かったらどうなっていたか……。
草分の上富良野尋常小学校は複式の三学級で、校長は榎本先生であった。この頃から肩掛け鞄になった。
五年生頃から、夏は燕麦刈りや草刈りなど家の手伝いをさせられたが父は、自分は勉強したくても家の都合で出来なかったので、子供は学校にやりたいと高等科まで上げてくれ、兄達は日新から二里(八㌔)の道を歩いて通った。高等科に進む人は少なかったので、私の時は一・二年生の女子が一クラスで四十人ぐらい、受け持ちは桜井先生であった。
運動が得意で、運動会にはあちこちの学校に走りに行った。当時、運動会はお祭りに次ぐ催しであり中でも他校リレーは花形で、それを目当てに部落からも大勢が見に来たものであった。ノートなど沢山の賞品を貰うので学用品は殆ど買わずに済んだ。
そんな私の血を引いたのか子供達もスポーツ好きで、長男の孫娘は走り高跳びで、全国高等学校体育連盟陸上競技大会に出場し、昭和五十九年に上富良野町からスポーツ奨励賞を貰っている。
掲載省略:写真〜高等科1年の時の十勝岳登山(昭和4年)
子供の頃の遊びは、お手玉や毯[まり]つきで、男は竹割や立橇[たちぞり](スキーを短かくした板の先きにロープをつけて、手で引いて舵を取りながら立って乗り、山の上から滑る)であった。
卒業後は家の仕事を手伝い、冬は補習科(上富良野小学校で裁縫や作法を教えた)に三年間通い、その後は個人の裁縫所にも行って自分の花嫁衣装も仕立てた。元禄の着物に羽織り、裾に一本の白線が入った袴と、履物は雪下駄で通った。
結婚・十勝へ
十九歳の十二月、高士の父に見込まれ、二十六歳であった三男の政一と結婚することになった。私の父は前年に亡くなり兄が親代りで、夫と兄は同級生だったので「あれは真面目な男だから行け」と兄に言われた。その後、長兄は大東亜戦争で北千島に行き戦死し、次兄は旭川の師範学校を出て教員をしていたが、昭和二十三年に病死した。
高士の父仁左エ門は十勝岳爆発で土地を失い、復興の見込みが無いと読んだのか、十勝方面に耕作地を求め一年程あちこちを歩き回り当時は中士幌で農業を営んでいたが、上富良野に小作地があったので時々様子を見に来ており、小林八百蔵さん宅に立ち寄った際に、たまたま私が用事に行ったことろを見染められ、見合いだけでもいいと言われたが結局は十勝に嫁ぐ事になった。
庵本髪結さんで、私が縫った留袖で花嫁仕度をして貰い、汽車に乗って狩勝峠を越え一日がかりで士幌の駅に着いた。
夫の家は士幌で開いた田圃を小作にし、音更にも三十町歩の土地を小作にして、中士幌では両親、二人の弟と共に五町歩の水田と二町歩の畑を耕作していた。
翌年、長女を出産したが、十勝は雪が少なく風が強いところで、オムツは冬でも外に干した。ランプ生活ではあったが、水は家の中に手押しポンプがあり、普通の農家の暮しであった。
掲載省略:写真〜自分で縫った花嫁衣装をまとい嫁ぐ日のミドリさん(昭和10年12月)
帰郷・草分での生活
一年と言う約束であったが三年を過ごし、一族共々上富良野に戻る事になった。舅は上富良野に来た折には災害復旧の状況も見ていたので、先の見通しがついたのか十勝の土地を小作にしての帰郷であった。再興の望みは無いと言われた災害地もその頃は大分復旧しており、白樺林と化していた元の田圃を再び開いて耕作する事になった。
十勝に行った時は六人であったが、義弟達が結婚し子供が生まれ、私も何時しか四人の子供の親となり総勢十四人家族で、主婦の仕事も大変であった。
住いは現在の家の側[そば]にあったが水の便が悪く、裏の沢から湧水を桶に汲み上げ天秤で担いで運び、飲み水は大きな水瓶に溜めておくが、風呂の水汲みは大仕事であった。
冬は裏口の戸が凍りつき、毎日お湯を沸かして解かし、台所は寒いので下駄を履いてガタガタと歩き朝に出した漬物も昼には氷が張ってしまう程で、暖をとるにも、ストーブの回りは両親と子供の指定席になっていて主婦の座る場所はなかった。
毎朝三升釜でご飯を炊き、おかずは野菜をどんと煮ておいたが、水田農家のお蔭で米のご飯が食べられた。
夫を亡くして
昭和三十三年六月、夫は肋膜炎[ろくまくえん]を患い旭川の厚生病院に入院したので娘が看病にあたり、水田五町歩と四町歩の畑を通い作しながら私が耕作していた。夫の病気は一カ月で治ると言われ安心していたが、翌年五月、五十歳で逝ってしまった。
夫亡き後、一人息子の長男・辰雄は高校二年生で働手がない為、内地から奉公人を雇ったが馬を怖がるので、私が馬を使い何とか田畑を耕したが、どのように作付けしたらいいのかも分らず、当時は、配合肥料などなく単肥だったので作物毎に合わせなければならず、肥料を選ぶのに先ず苦労した。冬の間に農業指導員のところに勉強に行き、岩田賀平さん、片井義也さんには随分お世話になった。夜、家族が寝てから必要量を計算し準備しておき、春に使う時に合わせたが、三町歩の畑に豌豆、小麦、燕麦、ビート、菜種、亜麻、クローバなど十種類もの作付けをするので、一つ一つ合わせるのは大変なことであった。
息子に引き継ぐ
夫が病気になった時、先ざきの事を考えたのか高校一年の息子に代掻きや、稲架[はさ]立ての仕事を教えていたが、父親に怒られ怒られ頑張っていた息子も昭和四十年に結婚した。
次の年、舅が九十四歳で亡くなり、四十二年から一切を息子に任せ、やっと安心した。
私も十年程前に体が震え出しパーキンソン病と診断され、札幌の安井病院に一年入院し良くなって家に戻ったが、一と月余りで再発し、今は動くのがやっとで「いよいよ動けなくなったらどうしようー」と心配になる事もあるが、家族に大事にされ唯一楽しみなテレビの前で過ごす毎日である。
上富良野に生まれ町の歴史と共に歩み、生涯を我がふる里に生きる幸せを感じながら……。