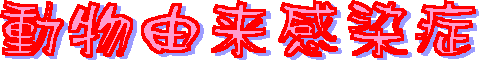
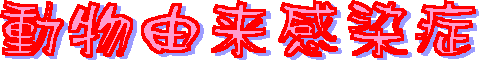
 動物由来感染症とは?
動物由来感染症とは? |
| 「動物由来感染症」とは、動物から人間へうつる感染症をあらわす言葉です。 「人畜共通感染症」、「人獣共通感染症」そして「ズーノーシス」といった言葉もありますが、厚生労働省は人の健康問題という観点に立って、この「動物由来感染症」という言葉を使っています。 人の感染症については医学が対応し、動物の感染症については獣医学が対応していますが、動物から人へ伝播する動物由来感染症については、医学と獣医学が協力して対応することが大変重要です。 |
 動物由来感染症の伝播 動物由来感染症の伝播 |
| 感染症がうつることを「伝播」といいます。 動物由来感染症における伝播とは病原体が動物から人間にうつってくる全ての途中経過をあらわします。 病原体の伝播は感染源である動物から直接人にうつる直接伝播と、感染源動物と人間との間に何らかの媒介物が存在する間接伝播の、大きく二つに分けることができます。さらに間接伝播は動物の体から出た病原体が周囲の環境(水や土壌など)を介して人間にうつるもの、感染動物体内の病原体を節足動物など(ベクター)が運んで人間にうつすもの、および人間が利用する畜産物が病原体で汚染されている場合に分けて考えることができます。 |
| ●直接伝播 |
| 咬み傷や引っ掻き傷からの病原体の侵入が典型的なものです。 口の周りや傷口をなめられてうつる場合もあります。動物の咳やくしゃみを直接受けたりすることで感染する病気もあります。 動物の体についている病原体も直接伝播の原因となります。 特に子供では動物に触って糞などで汚染した手を口に持っていくことで感染するルートもあると考えられています。 |
| ●環境媒介 |
| 病原体で汚染された水や土壌と接触したり飲んだりしてうつる動物由来感染症は多数知られています。 また排泄された病原体が風で舞い上がって空気を吸い込むことで感染するものもあります。 この感染ルートの特徴は、環境が病原体に汚染されていることには通常は気がつかないことです。 |
| ●ベクター媒介 |
| ノミ、ダニ、カ、シラミなどが感染動物から人間へと吸血などによって病原体を伝播することがあります。 これらの外部寄生動物をベクターと呼びます。病原体はベクターによって機械的に運ばれる場合とベクター体内で成熟する場合があります。 寄生虫に多い伝播に、卵や幼虫が巻き貝などの体内で成長して人間に感染するルートも知られています。 |
| ●動物性食品媒介 |
| 家畜や魚介類が病原体を持っている場合、熱を加えずに食べたりすることで動物由来感染症が伝播することがあります。 |
| <伝播経路と動物由来感染症>(表1) |
|
伝播経路 |
具体例 |
動物由来感染症の例 | |
|
直接伝播 |
咬傷 |
狂犬病 | |
|
間接伝播 |
環境媒介 |
水系汚染 |
クリプトスポリジウム症 |
|
ベクター |
ダニ |
回帰熱 | |
|
動物性食品 |
肉 |
有鉤条虫症 | |
| 動物由来感染症の病原体の多くは本来は動物が持っているものです。 このため動物の種類ごとに分けて考えることで、さまざまな動物由来感染症の特徴を見いだすことができます。 こうした種類分けにはもちろん例外や中間的なものもあります。 |
| ●ペット |
| 人間とペットは非常に密着した距離で生活しているため、ペット由来の動物由来感染症の特徴の一つに咬まれたり引っ掻かれたり、また気づかずに排泄物(糞や尿)に触れた手を口にもっていったりしてうつる直接伝播(後述)が多いことがあります。 ところでここ数年、生活や価値観が多様化してきたのに伴って従来のペットとは異なる動物(いわゆるエキゾチックアニマルと呼ばれます)をペットとして飼育する人が増えています。しかしエキゾチックアニマルが、これまで知られていない未知の感染症も含めてどのような感染症を持っているのか、知られていることは多くありません。 数千年以上もの時間をかけて人間との共同生活に必要な安全性が確立されてきたイヌやネコでさえ、時として彼ら特有の感染症を人にうつすことがあることを考えると、エキゾチックアニマルの持っている危険性の大きさは容易に想像できます。 |
| ●野生動物 |
| 野生動物は本来は人間とは異なる生活圏内で生きているために直接人間に感染症をうつす機会は少ないと思われがちです。 しかし、タヌキ、イノシシ、サル、キジ、コウモリ、鳥類など、人間と近い距離で生きている野生動物もたくさんいます。またレクリエーション等で野外活動をする場合に野生動物の世界に足を踏み入れる機会はよくあります。また、上に述べたエキゾチックアニマルはたとえ人間に飼育されていても野生動物であることに違いはありません。 |
| ●都市型野生動物 |
| ネズミ、ハト、カラスなどは都市型野生動物と呼ばれることがあります。 これらの動物は人間に管理されていないという意味では野生動物のライフスタイルを持っています。しかし一方で彼らの食生活と住生活は人間社会に強く依存しており、集団の密度も他の野生動物に比べて高い都市型です。 このため動物本来の感染症に加えて、人間の感染症を拡げる危険性も有しています。 このような都市型野生動物はほとんど全ての人間の生活圏で見ることができます。 |
| ●学校動物 |
| 学校や幼稚園、および老人施設などで飼育している動物を仮に学校動物と呼ぶことにします。 学校動物は、次に説明する展示動物とペットとの中間的な性格を持っていると思われます。 学校動物は児童・園児や老人施設利用者など、抵抗力の弱い人達との接触の機会が多いことから、その健康管理に十分注意する必要があります。 |
| ●展示動物 |
| 動物園や水族館など、観客に見せることを主な目的としている施設で飼育されている動物のグループです。 イヌやネコなどの身近な動物から世界の珍獣までさまざまな種類が飼育されていますが、主要な施設では比較的健康管理に注意していることと、人間との直接接触が限られていることなどから動物由来感染症の感染源となることは少ないと思われます。 |
| ●家畜/魚介類 |
| われわれ人間は牛や豚などのさまざまな種類の家畜や魚介類を食用目的などの畜産製品として利用していますが、肉、魚などが動物由来感染症の原因となる可能性があります。 |
| ●実験動物 |
| 過去には研究施設などで実験用の動物が汚染されていたために人間への感染源となった例もありました。 |
|
動物由来感染症の原因となる病原体には、大きいものでは何センチ(時には何メートル)もある寄生虫から、電子顕微鏡を用いなければ見ることのできないウイルスまで、さまざまな病原体があります。 |
| <病原体の種類と動物由来感染症> |
|
病原体の分類 |
動物由来感染症の例 |
|
ウイルス リケッチア・クラミジア 細菌 真菌 原虫 寄生虫 |
狂犬病、日本脳炎、インフルエンザなど Q熱、紅斑熱、オウム病など ペスト、サルモネラ症、レプトスピラ症など 皮膚糸条菌症、クリプトコックス症など バベシア症、トキソプラズマ症、アメーバ症など イヌ・ネコ回虫症、エキノコックス症、吸虫症など |
| 同じグループの病原体であっても自然界で病原体を保有している動物種の違いによってわずかづつその性質が異なる場合もあります。 このため、きわめて多数の種類の病原体が動物由来感染症の原因となることが知られています。 |
| 世界的にみると300近くの動物由来感染症を数えることができますが、そのうち日本には数十〜100くらいがあると思われます。 日本に動物由来感染症が比較的少ない理由としてつぎのことが考えられます。 |
| ●日本は全体として温帯に位置しているため、熱帯・亜熱帯地域に多い動物由来感染症がほとんどなく、また島国であるため周囲からの感染源動物の侵入が限られます。これらの地理的要因のため野生動物由来感染症やベクター媒介性の動物由来感染症が比較的少ないと思われます。 |
| ●日本では獣医学領域が中心となって家畜衛生対策を徹底して行ってきました。この結果家畜を感染源とする動物由来感染症の中には現在では日本ではみられなくなったものが多数あります。 |
| ●日本人が、手洗いの励行や(収穫した米を守るために)ネズミ対策をとってきたことなど、日常的な衛生観念の強い国民性であるといわれることも関係があるかも知れません。 しかし現在、世界では従来知られていないたくさんの感染症が次々に見つかっています(ニパウィルス感染症など)。そしてその多くが動物由来であることも分かってきました。 |
| 人間はペットや家畜などさまざまな動物とある意味で共存して生活しているという現実をふまえて、できることなら動物との絆を断たずに動物対策を行い、病原体の伝播を断つ方法を考える必要があります。 |
近年のペットブームにより、多くの人々がペット動物を飼養するようになってきています。 我が国では、約3分の1の家庭で何らかのペット動物が飼養されており、その種類は多い順から、犬、猫、小鳥となっていますが、これらペット動物がかかる疾病の中には、狂犬病、オウム病、レプトスピラ症、トキソプラズマ症等人にも感染する人畜共通伝染病があり、人と動物の快適な共存の前提としてこれら疾病の感染予防のための方策を推進することが重要です。 ペットは可愛いですが、反面、動物由来感染症が人にうつる感染媒介であるといったことも十分に理解する必要があります。 これは飼い主の責務です!(動物に触れた後に手指の消毒をするだけでなく、動物に病気を移さないためにも動物を触る前にも手を洗いましょう!) 人間は多くの生物と共生している事実を忘れないで、幅広い視野に立って感染症の対策をたてていく必要があります。 |